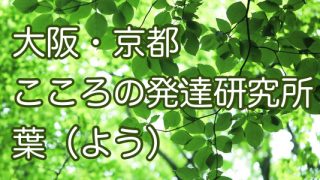公認心理師とは
公認心理師は日本で唯一の心理専門職の国家資格です。
平成27年9月9日に公認心理師法が成立し、平成29年9月15日に施行され、平成30年9月9日(北海道胆振東部地震により一部の人は12月16日)に第1回目の国家試験が実施されました。
その後、合格した方で、登録が完了した者から「公認心理師」と名乗ることができるようになっています。
2021年に公開された映画「ファーストラヴ」で、北川景子さんが演じる主人公の真壁由紀が公認心理師であることでも話題となっています。
こちらは島本理生さんの同名小説が原作となっているのですが、原作では臨床心理士となっています。
公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
- 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
- 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
- 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
- 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
つまり、「公認心理師」と名乗れるのは、年に1回行われる公認心理師試験に合格し、登録した者だけです(名称独占)。
しかし、「カウンセラー」はこれに含まれないため、誰でも名乗ることができます。
もちろん公認心理師の資格保持者が「カウンセラー」を名乗ることもありますので、心理の「カウンセラー」もさまざまということになります。
公認心理師試験の受験資格
公認心理師の受験資格は、公認心理師の養成過程をもっている大学に4年通い大学院の修士課程を修了する(Aルート)か、大学に4年通い実務経験を2年~3年つむ(Bルート)ことが原則となります。
しかし2022年9月までは移行措置として、大学や大学院で指定科目を修めていたり(Dルート)、現場経験が5年以上あるもので現任者講習を終えていたりした者(Gルート)(※現在は受験資格なし)にも受験資格を与えることができます。
最近の公認心理師試験の結果
公認心理師試験の合格率は、
第1回目79.6%(35,020人中27,876人合格)
第2回目46.4%(16,948人中7,864人合格)
第3回目53.4%(13,629人中7,282人合格)
第4回目58.6%(21,055人中12,329人合格)
第5回目48.3%(33,296人中16,084人合格)
第6回目73.8%(2,020人中1,491人合格)
となっています。
第5回目までは、移行措置のGルートの受験者が多数いたため、受験者数が多く、合格率が低くなっているようです。
合格基準点は6割程度とされていますが、今後、主流になっていくAルートが増えて行くことで受験者数や合格率は変わっていくでしょう。
また試験日は、第1回目は9月でしたが、その後はコロナ禍に入ったこともあり、開催月が安定せず、第7回目は2024年3月の開催予定となりました。今後も他の多くの医療系国家資格同様に2月~3月頃の実施になるのではないかといった予測がなされています。
公認心理師の職能団体
また多くの国家資格は、自己の専門性の維持・向上や、専門職としての待遇や利益を保持・改善するために職能団体に所属し、団体が開催する研修会に参加したり、団体が発行する会報で情報収集を行ったりします。
現在、公認心理師の職能団体は、「一般社団法人日本公認心理師協会」と「一般社団法人公認心理師の会」と2つあります。
また、まだ設立されたばかりということもあり、公認心理師の職能団体は十分にその機能が果たせておらず、現在、公認心理師を取得した方々が自己研鑽のために研修を受けようと思うと、自力で探し出す必要があります。
そのため今後の動向を見ていく必要があります。
そして、都道府県の臨床心理士会が公認心理師会と合併しているところもあり、その場合は、都道府県の臨床心理士会・公認心理師会に所属されることで、研修会等の情報が得られるでしょう。
また、都道府県によっては、臨床心理士会に所属していなくとも、会員ページを閲覧することが可能となっており、そこから情報を得ることもできます。
公認心理師と臨床心理士の違い
これまで心理の資格の中で有名だった臨床心理士資格との違いは、①臨床心理士が民間資格であるのに対し、公認心理師が国家資格であること、②大学院修了が必須ではないこと、③学部での必要科目を履修しなければならないこと、④資格更新制度がないことです。
公認心理師では、更新制度がないため、一度取得をすれば、自主返還や資格剥奪にならない限り、ずっと資格を所持し続けることができます。
そのため、研修会や学会への参加といった自己研鑽が個人のモチベーションや所属の判断にゆだねられることになりそうです。
公認心理師の今後
国家資格ということで、特に公的機関での応募条件に、公認心理師が明記されることは多くなっていくと思います。
診療報酬の点数に公認心理師が明記されれば、医療機関での採用も増えるのではないでしょうか。
今後、公認心理師が活躍する場は広がっていくでしょう。
当研究所では、公認心理師の方や資格に関係なく対人援助職が学べる機会を多数ご用意しております。
勉強会の一覧はこちらをご覧ください。
当研究所は、公認心理師&臨床心理士資格所持者のカウンセラーが担当致します。
参考書籍
◎ 公認心理師試験対策グループ (著) 『第2回 公認心理師試験 問題と解説 』(学樹書院)

第2回公認心理師試験の過去問と解説集。現役の心理臨床専門家、精神科医による簡潔で明解な記載が特徴で、しっかり細部まで検討されています。序文にある通り、まだまだ対策がしにくい試験内容ではありますが、学習を効果的に進めていくためには欠かせない書籍です。